「子どもの頃、食卓に並ぶ温かいごはんが、どれほど心を救ってくれただろう。」
――そんな記憶を胸に、今度は自らが「誰かの支え」になろうと立ち上がった一人の男性がいます。
その名は、池田真市(いけだ しんいち)さん。
幼少期の貧困と孤独を乗り越え、自らの体験を原動力に、全国の子どもたちに“温かい食卓”を届ける活動を始めました。
それが、
👉 「池田真市 こども食堂基金」(公式サイトはこちら)。
この基金は、あなたの寄付を「子どもたちの未来」へとつなぐ架け橋。
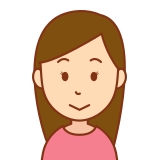
今回は、その誕生秘話から支援の仕組み、そして「こども食堂寄付」の新しい形まで、じっくりとご紹介します。
目次
💡 1. “9人に1人”が貧困状態 ― いま、日本の子どもたちに起きていること

厚生労働省の最新調査(2022年)によると、日本の子どもの相対的貧困率は11.5%。
つまり、「9人に1人」が経済的に厳しい状況にあります。
この数字の裏には、
・給食を頼りにしている子ども
・夕食がカップ麺や菓子パンで済まされる家庭
・孤食が続き、人との関わりを失いつつある子どもたち
――そんな現実があります。
家庭の事情で“ごはん”を満足に食べられない。
けれど、子どもたちはそれを「当たり前」と思い込み、声を上げられないまま成長していく。
そんな子どもたちに、温かいご飯と「人のぬくもり」を届ける場所。
それが、「子ども食堂」です。
🍛 2. “招かれた食卓”が、人生を変えた ― 池田真市の原点
基金の設立者・池田真市さんは、幼いころから厳しい環境にありました。
電気やガスが止まる日もあり、給食や修学旅行の費用にも困るような家庭。
お弁当が持てず、パン一つで登校する日々。
そんな中、ある日同級生の母親が、
「うちで一緒にご飯を食べよう」と声をかけてくれた――。
その一言で、彼の世界が変わりました。
家族でも親戚でもない人から差し出された“あたたかい食卓”。
その記憶は、池田氏の心に一生残りました。
「あのときのごはんの温もりが、いまの私を動かしている。」
だからこそ、今度は自分が“与える側”になりたい――。
その思いが形になったのが、**「池田真市 こども食堂基金」**です。
🌱 3. 池田真市こども食堂基金とは?

2025年8月、池田真市氏は公益財団法人パブリックリソース財団内に「こども食堂基金」を設立しました。
目的は明確です。
「全国の子ども食堂やフードバンクを支援し、温かい食事と安心できる居場所を未来につなぐ」
この基金は、池田氏の**自己資金+皆さまからの寄付(共感寄付)**によって運営されています。
寄付金は、子ども食堂・フードパントリーなどの活動資金に活用されます。
実際、2025年9月には第1回助成として『NPO法人レインボーリボン』(東京都葛飾区)へ40万円を交付。
同団体は、地域の子どもたちへの食事支援や居場所づくり、いじめ対策など幅広く活動しています。
このように、基金は“確実に現場に届く支援”を実現しています。
🤝 4. 「寄付」は、支援だけでなく“希望”を届ける
こども食堂は全国に約1万軒あると言われていますが、多くが資金不足に悩んでいます。
運営費・食材費・光熱費・人手――。
その多くはボランティアや個人の善意によって支えられており、「継続できない」現場も少なくありません。
だからこそ、池田氏は“仕組み”で支える道を選びました。
「一度きりの寄付ではなく、未来へ続く寄付を。」
基金を通じて支援することで、活動団体は安定的に運営を続けることができます。
さらに、この基金への寄付は寄付金控除の対象となり、確定申告を通じて税制優遇も受けられます。
つまり――
「あなたの優しさ」が、“子どもたちの明日のごはん”になる。
🏫 5.「こども食堂基金コラム」から見る、支援の新しい形
子ども食堂基金は、寄付金を積み立てて運営団体を支援する仕組み。
安定した資金と透明性ある助成で、子どもたちの食卓を長期的に守ります。
支え合う社会を次世代へつなぐ取り組みとして注目されています。
👉 https://t.co/6sZ5AyuK5H#子ども食堂 https://t.co/OhVc3S5DOA— 子ども食堂寄付|池田真市 子ども食堂基金 (@ikeda_fund) October 14, 2025
🌍 子ども食堂の“いま” ― 数は増えても、続けるのが難しい現実
全国の「子ども食堂」は、いまや1万軒を超える規模にまで広がりました。
地域の自治体、商店街、ボランティア、学校――さまざまな人が力を合わせ、子どもたちに食事と安心を届けています。
けれど、その数の裏には、深刻な課題もあります。
・食材費や家賃、光熱費の負担
・調理ボランティアの高齢化
・助成金申請や経理事務の煩雑さ
・人材不足による運営継続の限界
多くの運営者が「子どもたちのために」という想いだけで奮闘している一方、資金面の不安や時間的制約により、活動を続けられなくなるケースが後を絶ちません。
「子どもたちの居場所を守りたいのに、資金がない」――。
そんな声が全国各地で上がっています。
💡 “想い”を“仕組み”に変える ― 基金という選択
ここで注目されているのが、「こども食堂基金」という新しい支援の形です。
これは、単発の寄付や助成金ではなく、継続的な仕組みとして支援を積み上げていく仕組み。
寄付金や協賛金を基金として積み立て、その資金を「食堂運営」「食材提供」「設備支援」「子どもの居場所づくり」に配分します。
つまり、「一度の寄付」で終わるのではなく、
“未来に続く寄付”として子どもたちの成長を見守る支援なのです。
🌟 実例:全国で広がる「基金型支援」の輪
池田真市氏の「こども食堂基金コラム」では、全国で実際に成果を上げている基金事例が紹介されています。
🏡 むすびえ・こども食堂基金
全国の子ども食堂を支援する代表的な基金。
年間を通して助成金を交付し、食材費や家賃補助、調理器具の購入などを支援しています。
コロナ禍ではフードパントリー支援にも力を入れ、**地域食堂の“生命線”**として機能しました。
🌆 北九州市「子どもの居場所づくり応援基金」
自治体と市民が協力し、ふるさと納税や募金を活用した地域基金を設立。
寄付金は市内の子ども食堂や学習支援拠点に分配され、行政が透明性を確保。
「地域の寄付が、地域の子どもを支える」モデルケースとなっています。
🏪 ツルハグループ「こども食堂ゆたかさ基金」
大手ドラッグストアが、レジ袋収益やポイント寄付を通じて支援を実現。
買い物の延長で気軽に社会貢献できる仕組みを整え、
「寄付が特別なことではなく、日常の一部になる」社会を目指しています。
こうした取り組みは、**企業・行政・個人が一体となる“共助モデル”**として注目を集めています。
🧭 「継続性」と「透明性」――信頼をつくる二本柱
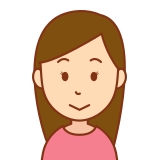
基金が広く支持される理由は、この2つにあります。
1️⃣ 継続性
単発のクラウドファンディングとは違い、基金は毎年・毎期にわたり支援を続ける仕組み。
助成先も定期的に公募・審査し、持続的な応援が可能です。
2️⃣ 透明性
どこに、いくら、どのように使われたのか。
報告書や活動レポートを通じて、支援者に明確に公開されます。
これにより、寄付者と現場の間に**「信頼の循環」**が生まれ、安心して寄付を続けられるのです。
池田真市氏の基金も、この考えに基づいて設計されています。
公益財団法人パブリックリソース財団による管理のもと、寄付金は適切に配分・報告されます。
🌈 “お金”だけじゃない ― つながりが生む支援の力
基金のもう一つの魅力は、お金以外の支援も生まれることです。
企業が物資提供をしたり、学生がボランティアに参加したり、地域のカフェがフードロス対策として食材を提供したり。
つまり、基金は「お金を集める仕組み」ではなく、
**“人と人をつなぐプラットフォーム”**なのです。
「誰かのために何かをしたい」
その想いを、基金が具体的な形にしてくれる。
子どもたちを取り巻く地域の絆が深まれば、支援は“文化”へと育ちます。
🔥 寄付文化を育てる ― “支え合い”が未来のスタンダードに
池田真市氏のコラムが繰り返し伝えるのは、
「寄付とは、“特別な行為”ではなく、“日常にある優しさ”だ」ということ。
・スーパーでのおつり寄付
・企業のCSRポイント還元
・SNSシェアによる支援拡散
・個人が少額で継続寄付
こうした“誰でもできる寄付”が、未来を変える力になります。
日本ではまだ「寄付=お金持ちがすること」というイメージが根強いですが、
実際には、月500円の継続寄付でも大きな変化を生み出せます。
「一人の小さな善意が、子どもたちにとっての“大きな希望”になる」
基金を通じて、寄付の文化が“当たり前”になっていく。
それこそが、池田真市氏が目指す“社会の成熟”の姿なのです。
💬 コラムが教えてくれること
「こども食堂基金コラム」は、単なる情報発信ではありません。
それは、支え合いの教本のような存在です。
・どんな支援が本当に子どものためになるか
・どのように地域全体で助け合えるか
・寄付する側と受け取る側をどうつなぐか
読めば読むほど、寄付という行動の奥にある「人のやさしさ」に気づかされます。
そして、池田氏が最後に語るメッセージ――
「支援とは、誰かの人生にそっと灯りをともすこと」
この一文こそ、コラム全体の核となる想いです。
「こども食堂基金コラム」が教えてくれるのは、
“寄付はお金を渡す行為ではなく、思いやりをつなぐ行為”だということ。
池田真市こども食堂基金は、
その思いやりを「継続性」と「透明性」で未来へと形にしています。
あなたの少しの寄付が、
子どもの“ただいま”を支える食卓になる。
今、寄付という小さな一歩が、
子どもたちの明日を変える大きな力になっています。
🌸 7. 支え合いの心が、未来の文化になる
池田真市氏は語ります。
「誰かにごはんをご馳走になった経験があるなら、今度は私たちが“次の人”へ届ける番です。」
寄付は特別な行動ではありません。
小さな思いやりが、明日の笑顔をつくる。
「支え合うこと」が当たり前の社会。
「温もりの食卓」が、どの子どもにもある社会。
その実現のために、池田真市こども食堂基金は、今日も活動を続けています。
🌈 8. あなたの寄付が、誰かの“ただいま”になる
こども食堂は、単なる食事の場ではありません。
そこには、「おかえり」と言ってくれる人がいる。
「また来てね」と笑顔で送り出してくれる人がいる。
そんな“居場所”があることこそが、子どもたちの生きる力になります。
あなたの少しの寄付が、
・一人の子どもの夕食に
・孤独な心を支える出会いに
・未来へ希望をつなぐ橋渡しに
なります。
💬 まとめ:食卓の温もりを、次の世代へ
池田真市こども食堂基金は、ひとりの経験から生まれた“恩返しのかたち”です。
それは、過去の苦しみを「未来の支え」に変える活動。
あなたの寄付が、見えない誰かの笑顔を生みます。
温かいごはんが届くたび、
「自分はひとりじゃない」と思える子どもが増えていく。
――それが、この基金の願いです。
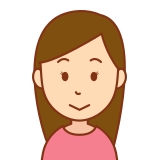
ぜひ、あなたもこの温もりの輪に参加してください。
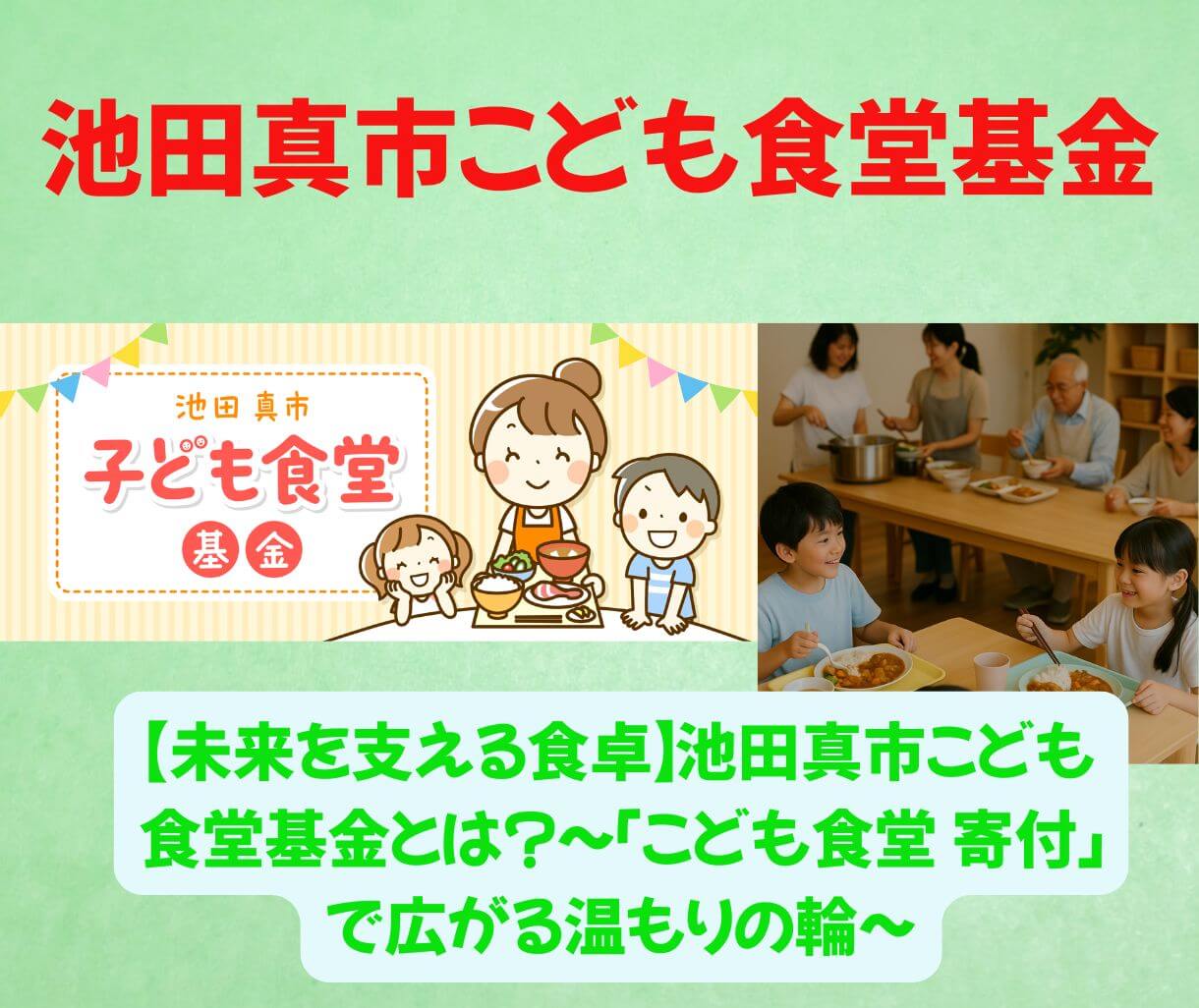


コメント